照明に興味を持って頂きありがとうございます。
“思わず試したくなってしまう照明デザインの魅力…”
照明の「心理作戦」
- 「ひかり」の使い方
- インテリア空間の提案スキルがワンランクアップする
- 住み手の暮らし方に合わせたインテリア空間提案の幅が広がる
- 専門知識と情報源を最短で手に入れることが出来る
ここには、照明の使い方、扱い方の考えを少し視点を変えてみるとどう世界が変わるのかが書いてあります。照明手法や器具選定の難しさを考える必要はありません。どんな空間にすると人々の心が動くのかを「ひかり」という目には見えないものがどんななのかを知って頂けたら。そう思ってます。
専門家を利用すること。
外部の専門家を巻き込む方法が得策という考え方。
知りたいことはGoogle君に聞く。それ何?と思ったらキーワード検索でなんでも手に入る時代ですから、専門家顔負けの知識や見地を有する人もいます。決して悪いことではありません。むしろ推奨すべきと考えます。好きなこと、興味のあることに突き進むにはさほど大きなパワーは必要ない時代です。走るのが好きな人は走るのが苦にならないのと同じです。でも、こんな経験はありませんか?
- Google検索したけれどしっくりくる答えが見つからない。
- その情報は本当なの?
- もっと他に良い方法があるかも・・・!
- で、結局何からはじめたらいいの?
こんな時は、「専門家」を使いましょう。
あなた個人の感覚を優先し、あなたの思うままに感じることが、あなたの生活を豊かにする一歩になる。と思います。
◆◆ 無料PDFダウンロード ◆◆
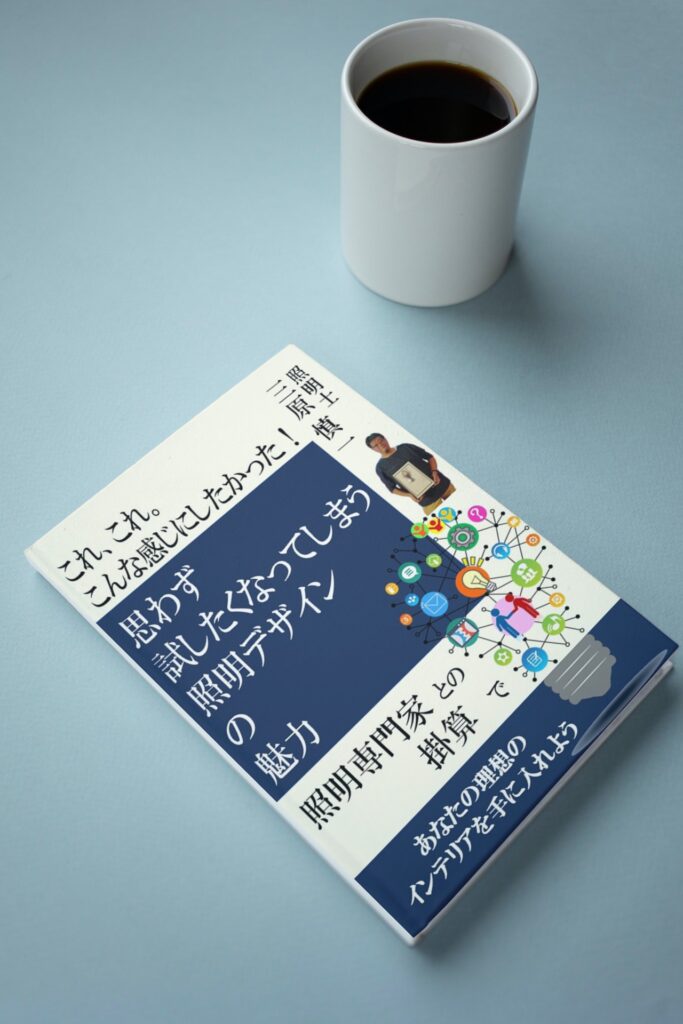
思わず試したくなってしまう
照明デザインの魅力
照明専門家との掛け算で、あなたの理想のインテリアを手に入れよう!
あなたのインテリアをひかりで演出したいから、
無料でどうぞ!
照明設計サポート業務
「照明設計の必要性を感じているけれど、自分で計画が出来なくて悩んでいる方へ。照明設計サポート業務であなたの照明計画をサポートします」
「照明サポート業務」は、照明設計の必要性を意識しているけれど、自身で計画が出来なくて悩んでいる人におすすめのサービスです。照明の基礎知識のおさらいから照明設計の応用・実践まで、あなたの照明計画をサポートするサービスです。照明設計サポート業務の特徴は、以下の通りです。
1. 照明知識をベースとした基本的な照明設計の考え方
2. 照明器具の選定
3. 具体的な照明施工事例から読み解くGOOD&BAD ← 一番人気
4. 自ら空間デザインを構成できるデザイナーへの一歩
照明設計サポート業務を利用することで、照明設計の必要性を意識しているけれど、自身で計画が出来なくて悩んでいるという問題を解決することができます。照明器具メーカーの無料プランニングに頼っていると、提案資料の良し悪しがわからない、いつも決まったメーカーを使っている、他のメーカーを比較する基礎知識がないというデメリットがあります。これらのデメリットを克服するためには、照明設計サポート業務を利用することがお勧めです。照明設計サポート業務は、照明の基礎知識のおさらいからスタートして照明設計の応用・実践へと駒を進めるイメージ。照明設計サポート業務は、照明カタログの見方が身に付き、各照明メーカーの特長を知ることが出来ます。インテリア空間デザインの提案の質が上がり、照明メーカーの無料プランから一歩抜け出すことができます。
照明メーカーへのプラン依頼を依頼する場合も、照明器具選定の基準がわかっていれば必要な要望をオーダーすることも可能。